こんにちは、獣医師まるです。

症状があるのに検査してくれなかった。ちゃんと診てもらえていない気がする。

検査もせずに薬だけ出して様子見と言われた。本当に大丈夫?
そんな不安を感じたことはありませんか?
実は私も獣医になる前に同じような経験があります。
家に帰ってから、体調のすぐれないペットの様子を見ながら、不安でいっぱい。
なんだかモヤモヤ…。
今回はこんな悩みをお持ちの方に向けて、動物病院で「検査してくれない」と感じたときに考えられる理由や、獣医師がどう判断しているかについて解説します!
なぜ検査をしないことがあるの?
まずは検査をしないと判断した獣医視点の理由を挙げてみます。
検査がまだ必要ないと判断した
症状が軽かったり、一時的な変化が疑われる場合は、まず生活環境の見直しやお薬で様子を見てから判断することがあります。
たとえば、「軽い下痢があるけど元気・食欲あり」といったケースでは、すぐにすべての検査をせず、まずは整腸剤や食事管理から始めることもあります。
今後の経過を見てから検査する予定
「今は見守って、改善しなければ次の検査をします」といった段階的な診療を行うこともよくあります。
まずお薬を飲んでみて、あるいは注射を打ってみて、改善なければ追加で検査をする場合もあります。
お薬や注射で反応が見られるかどうかも、診断を確定するのに重要なポイントとなります。
現在の症状から考えられる病気が、緊急を要するものであればすぐに検査が必要ですが、そうでなければ段階を踏んで検査を進めることがあります。
検査の負担を考慮している
動物にとって、検査そのものがストレスになる場合があります。
採血や麻酔が必要な検査は、動物の体調によっては慎重に進める必要があります。
また、検査内容によってはかなり高額になることもあります。
過剰な検査をせず、必要な検査だけを見極めて負担を軽減するのも大事な判断です。
検査には順序と条件がある?
動物の検査は内容によりますが、思いついたときにいつでもできるものではありません。
適切な条件やタイミングが必要です。
例えば、
- さっき尿をしたばかり
→ 尿検査用のサンプルが取れません。また膀胱の超音波(エコー)検査は、尿が溜まっているときと溜まっていない時とでは、見え方が変わってしまいます。 - 食後すぐ
→ 一部の血液検査の項目で、実際より高い値が出てしまうことがあります。(例:BUN、TP、TCHO、TG、GLU)また、麻酔を使う検査も絶食が必要です。
適切なタイミングで検査を行わないと、意味のある結果が得られないのです。
実際の例
【段階的に検査を進めたケース】
「食欲が落ちた」とのことで来院したワンちゃん。
まずは問診・視診・触診・聴診を行い、初期段階として血液検査を実施しました。
明らかな異常はなく、環境改善の指導とお薬で様子を見ることに。
しかし2日後も改善が見られず、再来院。
レントゲン検査を行うと腸にやや異常像。
さらに誤食の可能性があるとのことでバリウム造影検査を数時間かけて行い、ようやく原因を特定できました。
このように負担を最小限にしつつ、必要に応じて検査を進めていくのが一般的な診療スタイルです。
外注検査は時間がかかることも

血液検査したのに結果は来週わかると言われた。なんでそんなに時間かかるの?
動物病院では、すべての検査を院内で完結できるわけではありません。
以下のような検査は、外部の検査センターに依頼(外注)することがあり、結果が出るまでに数日〜1週間ほどかかることがあります。
- ホルモン検査
- アレルギー検査
- 病理検査(組織の一部をとって調べるもの。腫瘍など)
そのため、結果を待っている間に症状が悪化しそうな場合は、検査結果を待たずに治療を先に始めることもあります。
検査しない理由は他にもある
経験で診断できることもある
長年の経験から、検査をせずにある程度の診断ができる獣医師もいます。
とはいえ、検査を省略されることに不安がある場合は、その理由や診断根拠をしっかり聞いておくと安心ですね。
病院に検査設備がない場合も
動物病院によっては、検査キットや機器がそろっていないこともあります。
その場合、他の病院を紹介されたり、外注に頼る形になることも。
もし検査してもらいたい内容が決まっているのであれば、来院前にその設備があるのかどうか、電話などで確認してみると良いと思います。
見過ごし(ミス)の可能性もゼロではない
獣医も人間です。まれに見落としがあることも。
症状が改善しない、説明に納得できない場合は、他の先生に診てもらったり、他の病院に相談するのも一つの選択です。
検査結果も100%ではない
実は結果が100%信用できる検査は多くありません。
レントゲンやエコーなどの画像検査も、なんでも見えるわけではありません。
血液検査も状況によりブレは生じます。
顕微鏡を使った検査も、見ている部分は一部だけです。
また、たった1日でも結果が大きく変わることもあります。
獣医師により考えは様々ですが、皆必要なタイミングで必要だと思う検査を行っています。
飼い主さんが必要だと思う検査と、獣医が必要だと思う検査にズレが生まれることもあるかもしれません。
検査より治療を優先するべき状況
もし動物の体調が深刻で、一刻も早く治療をしなければ命に関わるような状況だった場合、治療の開始が優先されることも。
治療を進めながら、原因を知るために同時進行で検査をするケースもあります。
不安なときは方針を確認しよう!
もし「検査しなくて大丈夫なの?」と感じたら、以下のように聞いてみてください。
「今は検査しないとのことですが、改善しない場合にはどんな検査を行う予定ですか?」
「検査の結果待ちですが、このまま治療を進めて大丈夫でしょうか?」
「不安があるのでレントゲン検査してもらいたかったのですが、可能ですか?」
獣医師は、動物の状態や検査の条件を見ながら診療していますが、飼い主さんの不安を取り除くことも大切な役割です。
モヤモヤは我慢せずに、遠慮なく聞いてみてください!

まとめ
検査しない=放置ではありません。
動物病院で「検査してくれない」と感じる場面でも、そこには理由があります。
症状の段階、タイミング、動物の負担、検査条件などを慎重に見極めて判断されているのです。
ただし、不安なときには獣医師に遠慮せず確認し、「次の一手」を一緒に考えていきましょう!

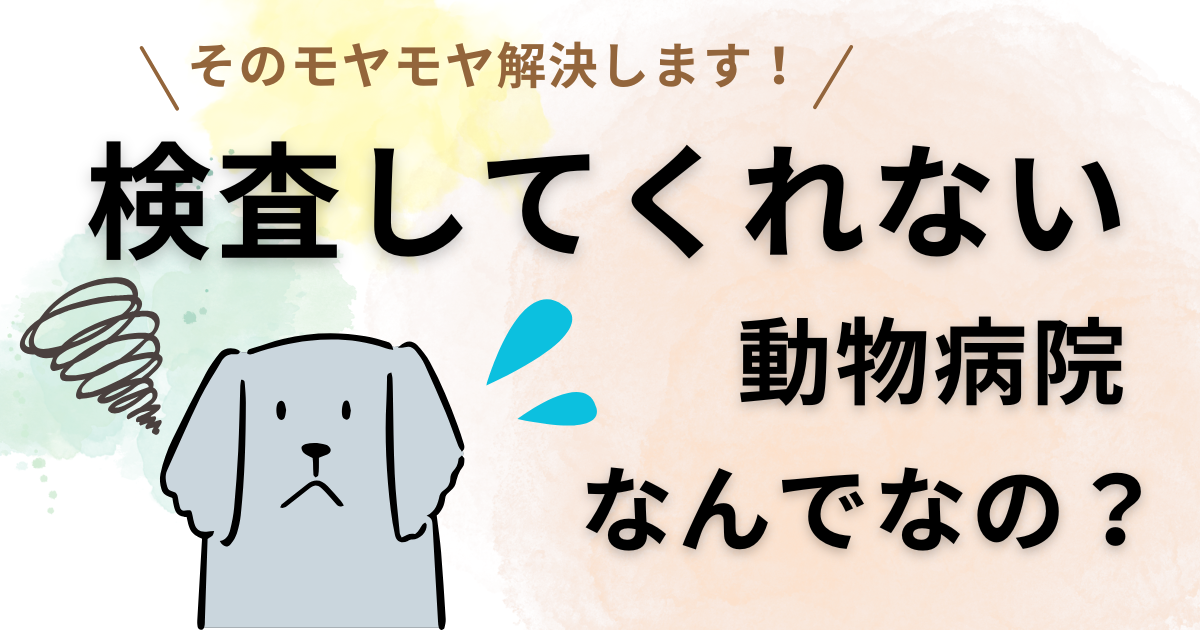
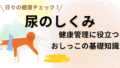
コメント